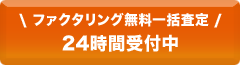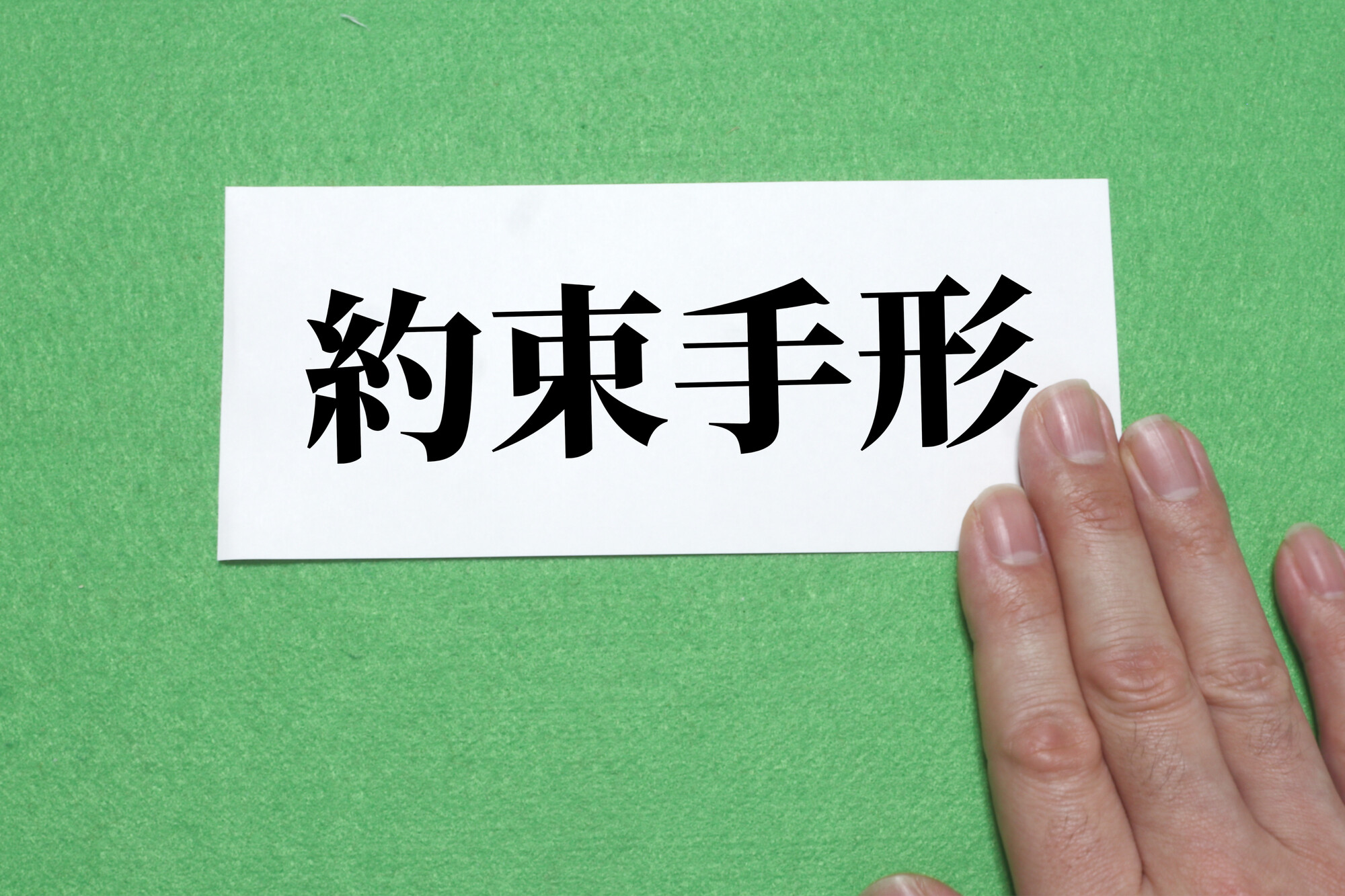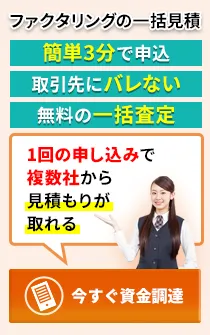公開日:2025年10月24日 更新日:2025年10月31日

建設業における資金調達手段として注目される「でんさい(電子記録債権)」と「ファクタリング」。本記事では、両者の仕組みや導入条件、コストの違いをわかりやすく解説します。
さらに、下請け・元請けそれぞれの立場での活用方法や注意点、どちらが自社に適しているかを判断するためのヒントも紹介。資金繰りに悩む建設業の経営者・担当者の方に向けた実践的な内容です。
この記事の内容
この記事のポイント
建設業における資金調達手段「でんさい」と「ファクタリング」の違いや活用法を、立場別にわかりやすく解説します。
- 元請けは手形廃止に備え、でんさい導入を進める動きがある
- 下請けは資金繰り対策としてファクタリングを活用しやすい
- でんさいは支払いの電子化・業務効率化に有効
- ファクタリングは信用情報に影響せず、即日資金化も可能
- 自社の立場やニーズに応じた手段選びが重要
でんさい(電子記録債権)とファクタリングの違い

建設業における資金調達手段として注目される「でんさい(電子記録債権)」と「ファクタリング」は、仕組みや利用条件、導入の手間に大きな違いがあります。
どちらも資金繰り改善に役立つ方法ですが、自社の立場や取引環境によって適した選択肢は異なります。
以下では、両者の特徴を比較しながら、導入前に押さえておきたいポイントを整理します。
違い①:仕組みと資金化の流れ
でんさい(電子記録債権)とファクタリングは、いずれも売掛債権を資金化する手段ですが、仕組みや流れに大きな違いがあります。
でんさいは、元請けが支払い債務を電子記録として登録し、受取側がその債権を金融機関で割引・譲渡することで資金化します。一方、ファクタリングは、受取側が保有する請求書や売掛債権をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する方法です。
以下の表で両者の流れを比較します。
| 比較項目 | でんさい(電子記録債権) | ファクタリング |
|---|---|---|
| 債権の発生元 | 元請けがでんさいネットに記録 | 受取側が発行した請求書・売掛債権 |
| 資金化の主導者 | 受取側(下請け)が金融機関に割引依頼 | 受取側(下請け)がファクタリング会社に売却 |
| 資金化までの流れ | 元請け→でんさい記録→受取側→金融機関割引 | 受取側→ファクタリング会社→現金受取 |
| 必要なシステム・契約 | でんさいネットへの登録・金融機関との契約 | ファクタリング会社との契約のみ |
上の表のように、でんさいは元請けの協力が不可欠である一方、ファクタリングは受取側主導で柔軟に資金化できる点が特徴です。
次項では、対象企業や利用条件の違いを見ていきます。
違い②:対象企業と利用条件
でんさいとファクタリングは、利用できる企業の立場や条件に違いがあります。
でんさいは元請け企業が導入していることが前提で、下請け企業はその記録債権を受け取る形になります。一方、ファクタリングは下請け企業が主導して利用でき、元請けとの取引に関係なく資金化が可能です。
導入のハードルや柔軟性にも差があるため、自社の立場に応じた選択が重要です。
以下の表で比較してみましょう。
| 比較項目 | でんさい(電子記録債権) | ファクタリング |
|---|---|---|
| 主な利用企業 | 元請け企業(支払側) | 下請け企業(受取側) |
| 利用開始の条件 | 元請けがでんさいネットに登録済みであること | 売掛債権(請求書)が存在すれば利用可能 |
| 導入の主導者 | 元請け企業が導入し、下請けが受け取る形 | 下請け企業が主導して契約・利用できる |
| 柔軟性・即時性 | 導入・運用に時間がかかる | 即日資金化も可能で柔軟性が高い |
このように、でんさいは元請け企業の体制に依存する一方、ファクタリングは受取側が自社判断で利用できる点が大きな違いです。
次は導入・利用にかかるコストや手間について見ていきましょう。
違い③:導入・利用にかかるコストと手間
でんさいとファクタリングは、導入や利用にかかるコスト・手間にも違いがあります。
でんさいは金融機関との契約やシステム導入が必要で、元請け企業の協力が前提となるため、初期対応に時間と費用がかかります。一方、ファクタリングは書類が整えば即日対応も可能で、契約も比較的シンプル。ただし、手数料は事業者によって異なり、債権の信用度によって変動します。
以下の表で両者の導入負担を比較してみましょう。
| 比較項目 | でんさい(電子記録債権) | ファクタリング |
|---|---|---|
| 初期導入の手間 | 金融機関との契約・システム導入が必要 | 書類提出と契約のみで利用可能 |
| 利用開始までの期間 | 数日〜数週間(社内調整・登録作業あり) | 最短即日(事業者によって異なる) |
| 手数料の目安 | 金融機関によって異なる(数千円〜) | 売掛債権の信用度に応じて変動(1〜20%程度) |
| 対応の柔軟性 | 元請け企業の導入状況に依存 | 受取側主導で柔軟に利用可能 |
上記の表のように、導入のスピードや柔軟性を重視するならファクタリングが有利ですが、でんさいは長期的な支払い管理の効率化に向いています。
次の章では、自社に合う資金調達方法について見ていきましょう。
自社に合う資金調達方法はどちら?

資金調達方法として「でんさい」と「ファクタリング」のどちらが適しているかは、企業の立場や取引環境によって異なります。
元請けか下請けか、取引先の体制や資金ニーズによって選択肢が変わるため、それぞれの特徴を理解したうえで、自社に合った方法を見極めることが重要です。
以下では、向いている企業の条件や対応可能な金融機関・事業者について詳しく解説します。
でんさいが向いている企業の条件
でんさいは、一定の業務体制や取引環境が整っている企業に向いています。特に元請け企業で、支払い業務の効率化や手形廃止への対応を検討している場合に有効です。
以下のような条件に当てはまる企業は、でんさいの導入を前向きに検討する価値があります。
- 元請けとして複数の下請け企業に定期的な支払いを行っている
- 既存の手形取引を電子化したいと考えている
- 取引先(下請け)がでんさいネットに対応している、または導入意欲がある
- 支払い業務を効率化し、事務負担や郵送コストを削減したい
- 金融機関との契約やシステム導入に対応できる社内体制がある
でんさいが利用可能な金融機関
でんさいは、でんさいネット(一般社団法人全国銀行協会が設立した「株式会社全銀電子債権ネットワーク」の通称)によると、現在、全国の金融機関のうち約490行が取り扱っています。
都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合・JAバンクなどが参加しており、地域や業態を問わず幅広く対応しています。ただし、すべての支店で利用できるとは限らず、事前に取引金融機関への確認が必要です。
ファクタリングが向いている企業の特徴
ファクタリングは、資金繰りの改善を図りたい企業や、売掛債権を早期に現金化したい企業に向いています。特に下請け企業や中小企業にとっては、柔軟かつ迅速な資金調達手段として有効です。
以下のような特徴に当てはまる企業は、ファクタリングの活用を検討する価値があります。
- 売掛債権(請求書)を保有しており、入金までの期間が長い
- 手形割引の代替手段を探している
- 銀行融資の審査が通りにくい、または時間がかかる
- 急な資金ニーズに対応したい(仕入れ・人件費など)
- 元請け企業との取引実績があり、債権の信用力がある
ファクタリングの提供事業者と対応範囲
ファクタリングは、銀行系・専門業者・オンライン完結型など多様な事業者が提供しており、全国対応や即日資金化など柔軟性の高いサービスが特徴です。
また、ファクタリングは事業者によって手数料や対応スピードが異なるため、複数社を比較検討することをおすすめします。
「一括見積サービス」を利用すれば、手間も時間も節約でき、以下のようなメリットがあります。
- 自社の条件に合った複数のファクタリング会社を一度に比較できる
- 同じ情報を何度も入力する面倒がない
- 最短即日で条件提示が届き、急ぎの資金化にも対応しやすい
- 信頼できる事業者のみ紹介されるため安心して選べる
- 4時間いつでも利用可能で、時間の制約が少ない
一括見積を活用することで、よりスムーズかつ確実な資金調達が可能になります。
下請け・元請けで異なる資金調達の実態と課題

建設業では、元請けと下請けで資金調達の手段や課題が大きく異なります。
元請けは支払い管理の効率化を重視し、でんさい導入を検討する一方、下請けは資金繰りの安定化が急務であり、ファクタリングの活用が現実的です。
それぞれの立場に応じた選択肢と、導入時に直面する課題を整理していきます。
下請け企業が抱える資金繰りの悩みとファクタリング活用
下請け企業は、工事完了から入金までの期間が長く、資金繰りに悩みやすい傾向があります。特に手形取引や支払いサイトが長い場合、仕入れや人件費の支払いに支障をきたすことも。
下請け企業によくある悩みをピックアップしてみました。
- 元請けからの入金が月末や翌月末で遅い
- 手形の割引率や期日が不安定
- 銀行融資の審査が通りにくい
- 急な資材購入や人件費に対応したい
こうした課題に対し、ファクタリングは売掛債権を早期に現金化できる有効な手段です。ファクタリングは最短であれば即日現金化が可能なため、資金繰りの安定化に向け、柔軟な選択肢として注目されています。
元請け企業がでんさいを導入する背景と目的
元請け企業がでんさいを導入する背景には、業界全体の支払い業務の効率化と法制度の変化があります。特に建設業界で長年使われてきた紙の手形・小切手は、2026年度末(2027年3月末)に正式廃止される予定であり、電子化への対応が急務です。
でんさいは、支払いの記録・通知・譲渡がすべてオンラインで完結するため、事務負担の軽減や支払い漏れの防止にもつながります。
元請け企業がでんさいを導入する主な理由をピックアップしてみました。
- 手形・小切手廃止への対応
- 支払い業務の電子化と効率化
- 下請け企業への支払いの透明性向上
- 郵送・印紙代などのコスト削減
- 支払履歴の一元管理による内部統制強化
こうした背景から、元請け企業ではでんさい導入が進んでいます。
※紙の手形・小切手廃止については、「【建設業の資金調達】紙の手形・小切手廃止は「でんさい+一括ファクタリング」で乗り切る!」のコラムも参考になさってください。
でんさいを拒否したい理由は立場で異なる
でんさいネットによると、でんさいの発生記録請求件数の業種別シェアは、製造業46%、卸売小売業38%に対して、建設業は11%。
参照:でんさいネット「建設業界における でんさいの普及状況」
でんさいは便利な仕組みですが、導入や利用を拒否したい建設業者は少なからずいます。その理由は元請け・下請けで異なります。
下請け企業側の主な拒否理由は以下の通りです。
- 取引先ごとに運用ルールが異なり、管理が煩雑になる
- でんさいネットへの登録やシステム導入が負担
- 金融機関での割引手続きが面倒、手数料もかかる
元請け企業側の主な拒否理由は以下の通りです。
- 社内の支払い体制やシステム変更にコストがかかる
- 取引先(下請け)の理解や対応が進まず、運用が難しい
- 手形廃止まで時間があるため、急いで導入する必要性を感じない
こうした背景を踏まえ、導入判断には双方の事情をすり合わせることが必要でしょう。
でんさいとファクタリングの違いについてよくあるご質問
でんさいとファクタリングの違いに関して、建設業界から寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。
Q.1 でんさい割引の仕組みとは?手形割引との違いを知りたい。
A.1 でんさい割引とは、電子記録された債権(でんさい)を金融機関に持ち込み、期日前に現金化する仕組みです。手形割引と異なり、紙の手続きが不要で、記録・譲渡がオンラインで完結します。印紙代や郵送費が不要で、紛失リスクも低減できるのが特徴です。
Q.2 ファクタリングは信用情報に影響するでしょうか?
A.2 ファクタリングは借入ではなく債権の売却にあたるため、通常は信用情報に記録されません。一方、でんさい割引は金融機関との取引履歴として信用情報に反映される可能性があります。信用情報への影響を避けたい企業には、ファクタリングの方が柔軟な選択肢となります。
Q.3 でんさい+ファクタリングで資金調達する手順は?
A.3 でんさいとファクタリングを組み合わせることで、電子記録債権をより早く資金化できます。主な流れは以下の通りです。
- 元請けがでんさいを発行(電子記録)
- 下請けがでんさいを受領
- 下請けがファクタリング会社にでんさいを譲渡・売却
- 審査後、ファクタリング会社から資金を受け取る
この方法により、でんさいの支払期日前でも現金化が可能になります。
まとめ:でんさいもファクタリングも自社の立場と資金ニーズに応じた選択が重要
でんさいとファクタリングは、いずれも資金調達の有効な手段ですが、企業の立場や資金ニーズによって適した選択肢は異なります。
元請け企業には支払い業務の効率化や手形廃止への対応としてでんさいが有効であり、下請け企業には柔軟かつ迅速な資金化が可能なファクタリングが適しています。
導入にあたっては、相手企業との関係性や業務負担、信用情報への影響なども踏まえ、自社にとって最適な方法を見極めることが重要です。
 一括ファクタリング
一括ファクタリング